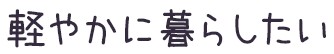- 投稿 更新
- (前に書いてた記事)

季節の変わり目には体調を崩しやすいといいます。
とくに秋から冬にかけて、ぐっと気温が下がってくると風邪をひきやすくなりますよね。肩こりや頭痛の症状が出たり、身体が重いな~しんどいな~と感じることはありませんか?
その体調不良は、「寒暖差疲労」かもしれません。
寒暖差疲労は、前日の気温との差が7℃以上あるときに起こりやすいといわれています。
ポカポカ陽気かと思えば木枯らしが吹き、小春日和が続いたかと思うと急に雪が降るような寒さ、そんな急激な気候の変化に身体がついていけないのですね。
ここでは、季節の変わり目に注意すべき寒暖差疲労の原因と対策について説明します。
もくじ
季節の変わり目にしんどい原因は寒暖差疲労?
日中は暖かかったのに朝晩はぐっと冷え込む…、昨日は寒かったのに今日は季節が戻ったように気温が高い…そんなことが繰り返される不安定な気候。
そんな急激な気温の変化に、体調を崩していませんか?
- 体が重く感じる、だるい
- 疲れやすい、疲れが残る
- 肩こり
- 体の冷え
- 顔のほてり、のぼせ
- 頭痛
- めまい
このような症状に悩まされたり、風邪をひいてしまったり。
身体的な不調だけでなく、食欲が出ない、よく眠れない、イライラする、落ち込む、などの精神的な不調に悩まされる人もいます。
このように気温の変化によって起こる体調不良を「寒暖差疲労」といいます。
寒暖差疲労は、7℃以上の気温差があると発症しやすくなります。天気予報で急に寒くなるといわれたときは注意しなければなりません。
寒暖差疲労は自律神経の乱れ?
寒暖差疲労の原因は、自律神経の乱れといわれています。
自律神経は、暑さ寒さに関係なく体の状態を同じにキープするためにはたらいています。
自律神経は交感神経と副交感神経からなり、暖かいときは副交感神経が血管を広げて熱を逃がそうとし、寒いときは交感神経が血管を縮めて体温調整をしています。
気温の差が激しいと、体温調整のためのエネルギーを多く使うことになり、身体に負担がかかって疲れてしまうのです。
自律神経は体温調節のほかにも内臓の動きや睡眠など、人間が意思によって動かせない部分をコントロールしている機関です。
自律神経のバランスが乱れて交感神経と副交感神経の切り替えがスムーズにいかないと、身体や精神面までいろいろな不都合が出てしまうのです。
急に寒くなると、血管を縮めて熱を逃さないようにしようとするので、血行が悪くなり肩こり、頭痛などの原因になります。
疲労がたまることで免疫力が低下し、風邪を引きやすくなったりもします。
寒暖差疲労の対策は?

寒暖差疲労を防ぐには、自律神経に無理をさせず身体に負担をかけないようにすることが大切です。
- 重ね着をして、脱ぎ着でこまめに温度調節をする
- シャワーですませず湯船でしっかり暖まるようにする
- 冷たい飲み物をひかえ、身体が冷えないようにする
- ストレッチなど軽い運動を行う
- 首、手首、足首の3つの首を温めて体温を逃さないようにする
とくに効果的なのが、首を温めることです。
自律神経は首を通っているので、首を温めて交感神経を下げることが自律神経のバランスを保つために有効なのです。
外出時や日中だけでなく、夜寝るときもスカーフやネックウォーマーを利用するとよいでしょう。
ウールのようにちくちくせず、体温調節の機能を持つ、シルクのネックウォーマーがおすすめです。
おわりに
季節の変わり目のしんどさには寒暖差疲労という理由があったのですね。
暖冬の年は、寒暖差が激しいともいわれています。
気温の上下に身体をまかせたままでは、自律神経がオーバーワークになってしまい寒暖差疲労の原因となります。
身体に負担がかかる気温差には、重ね着や入浴などで対策するようにしましょう。